オリジナリティを追求できる世界へ
みんなの夢をパッチワークでつないでいく
オリジナリティを
追求できる世界へ
みんなの夢を
パッチワークでつないでいく
2023年初夏、私からライターのManaさんにお願いしたインタビュー。
これまでの私と、これからの私を聞き取ってもらいました。
その記事をプロフィールとして掲載します。
Writing an Interview:Mana Wilson
2023年初夏、私からライターのManaさんにお願いしたインタビュー。これまでの私と、これからの私を聞き取ってもらいました。その記事をプロフィールとして掲載します。
Writing an Interview:Mana Wilson

バッグ作家、デザイナー、福祉と協業する人、民族布好き、編集者。
「kibi-ru ACTION」の嶋野詠子さんのことを、人々はいろいろな角度から表現する。“嶋野詠子”というひとりの人間なのに、関わり方によって見え方が違うのがおもしろい。いろいろな表情があるのは、それだけいろいろな人と関わってきたからだとも言える。
「私ね、とにかく“人”が好きなんですよ」
そう笑う彼女の半生を追いかける機会をもらった。
「kibi-ru ACTION」は、エスニック布を中心としたバッグ制作を行いながら、OEM制作、イベントやワークショップの企画、ブランディングサポートなど、幅広く活動しているブランドだ。詠子さんと同じく、多様な顔を持っている印象がある。詠子さんの出身地・博多の方言で「結ぶ」を意味する「きびる」と、「動く=アクション」をつなぎ合わせたのが、名前の由来。
結んで、動く——。
これまで歩んできた人生を一緒に辿ってみる。多彩な顔を持つ詠子さんと「kibi-ru ACTION」は、どうやって生まれ、歩み続けてきたのだろうか。

嫌いだった「職人気質」、魅せられた「書体」
嫌いだった「職人気質」、
魅せられた「書体」
「ペンキだらけの父を見ながら、『職人にだけは絶対になりたくない』って思ってたんですよ」
福岡県に暮らす両親のもとに生まれた詠子さんは、看板職人だった父の背中を見て育った。自宅の一階にかまえた作業場に充満するシンナーやペンキの匂い、汚れた服、そして「気に入るまで徹底的にやる」“職人気質”。
「こだわりが強すぎるし、頑固だし。世の中を上手に生きていくためには、もっと柔軟じゃなきゃって子供心にずっと思っていたんです。私はもっと上手に世間を渡っていくぞって」
それでも、お店の看板や印刷物などを手がける父の仕事は好きだった、と振り返る。趣味のような仕事のような、父の「スクラップブック作り」を手伝うのは、幼い詠子さんの楽しみでもあった。新聞やチラシから父が切り出したさまざまな“書体”を、ノートに糊付けしていく作業だ。今の時代はコンピューターでフォントを探せるけれど、当時は手書きが主流。父は自分の描ける「書体」を貯めていた。
「糊付けをしながら、書体っておもしろいなあって思っていましたね。形やバランスによって見え方が全然違う。その影響なのか、私は今でもどんな美術館に行くより、駅やショッピングモールにあるポスターを見るのが好きなんです。色や文字のバランスだったり、キャッチコピーだったり、見ていて全然飽きないんですよ」
職人の父のもと、駅のポスターを眺めていた少女が「デザイナーになりたい」と夢を語るようになったのは、自然なことだったのかもしれない。通っていた商業高校では当たり前のように就職する子が多いなか、デザイナーを目指す女子高生を周りの人たちは「そう簡単になれるもんじゃないよ」となだめるように笑った。

それぞれの気持ちがわかる、まとめ役の始まり
それぞれの気持ちがわかる、
まとめ役の始まり
ところが、周りの「デザイナーなんて……」という声をひっくり返す出来事が起きた。高校3年生で応募した『高校生デザインコンペ』で大賞を取ったのだ。一体どんなものを描いたんです?と聞いてみると、17歳の詠子さんが描いたのは「東京」だった。
「ヤシの木の中から、いろいろなものが飛び出してくる慌ただしい絵。九州の田舎にいて、東京に行ったこともない女子高生がイメージする東京でした。今思えば、キース・ヘリングによく似ている雰囲気だったかな。父が看板の書体を太く縁取るのと同じように、イラストを太い黒縁で囲って……」
この受賞で、詠子さんの進路は一変。就職予定だったのをやめ、博多駅近くにある「日本デザイナー学院」のグラフィックデザイン科に入学した。それまで反対していた大人たちは、「お前ならできる!」「がんばってこい!」と、手のひらを翻したというのだから、大人の言うことは当てにならない。
専門学校でも、詠子さんは持ち前のデザイン感覚と前向きさで道を切り開いていった。美術展での入賞の経歴や、卒業生代表としてスピーチしたことなどを聞けば、その様子が伝わってくる。そして、卒業と同時に、詠子さんはグラフィックデザイナーになっていた。学校に来ていた講師が経営する編集事務所に誘われたのだ。
「どうして私を引き抜いてくれたのかはわからないけれど。『うち来る?』って職員室で面接が始まって、そのまま入社しました」
憧れのデザイナーとして、雑誌や紙媒体のデザインを担当。ところが、一年も経たないうちに、今度は「書くほうもやってみない?」と誘われることになる。せっかくデザイナーになれたのに、という思いはなかったのか聞くと「なかった」と即答された。
「ずっと書体が好きだったから。キャッチコピーや見出しに憧れがあったんです。『私にできるのかな』って好奇心が勝った感じでしたね。私が憧れていたグラフィックデザインはいつも文字とセットだったから、ビジュアルと言葉、両方できたらもっと伝わるのかなという思いもありました」
ビジュアルで伝えるデザイナーと、言葉で伝えるライターの両方を経験し、最終的には編集という立場で全体の管理をする立場に。
「デザインもライティングも、私がやると正直60点くらいだなって思うんです。でも、全部をやったことがある立場として、現場の仕事がスムーズに流れるように段取りするのは得意でした。仕事のやりやすさが、最終的にクオリティにもつながりますからね」
ライターやデザイナー、フォトグラファーと関わる人が多い編集業務。それぞれの良さを引き出し、最大限の魅力的な作品を生み出す。その役割が、実は一番楽しかったのだと教えてくれた。

子どもの「通園バッグ」で燃えたクリエイター魂
子どもの「通園バッグ」で燃えた
クリエイター魂
その後も7年間、福岡でがむしゃらに働いていた詠子さんは、27歳のとき結婚を機に上京。現在も暮らしている埼玉県所沢市に居を構えた。それから2年ほどはリモートワークで編集の仕事を続けていたが、2002年に娘が生まれたことで、一度すっぱり仕事から離れることにしたという。
「それぞれの実家も親戚も九州で頼る先がなかったので、一旦は子育てに集中せざるを得ないという感じでした。まあでも、そのうちまた何かやるんじゃないかなっていう気はしていたんですけどね」
その“予感”は、思いのほか早く、3年後に的中することとなった。きっかけは、娘が幼稚園に入るときに「通園バッグ」を作ったことだ。幼稚園の荷物を入れるバッグ類は各家庭で手作りすることが多い。裁縫は中学校の家庭科以来だった詠子さんも、娘のバッグ作りのために安いミシンを買ったという。
「その時に作ったのは、手芸店で買ってきたキャラクターの布を使ったバッグ。それで火がついちゃったんですよね。別に一枚布で作ればいいのに、何種類かの布を合わせて切り替えしたり、あえて反対色の紐を探して手芸屋を回ったり。こだわり始めちゃったんです」
4年後に息子にも同じように登園バッグを作る頃には、オリジナリティの追求に拍車がかかっていた。指定の紐とは別で持ち手をつけたり、無地と柄を組み合わせたり。バッグ作りの完全な虜になっていた。
「子どもは『普通がいい』と言っているにも関わらずね……(笑)一枚布で作ったり、同じ色で統一しておけば無難なのに、一手間加えたくなってしまう。それをすることで味が出ると思ってしまったんですよねえ。本には載ってないようなオリジナルを作るのが楽しくて!」
そこにあったのは紛れもなく、父親譲りの「こだわり」だった。
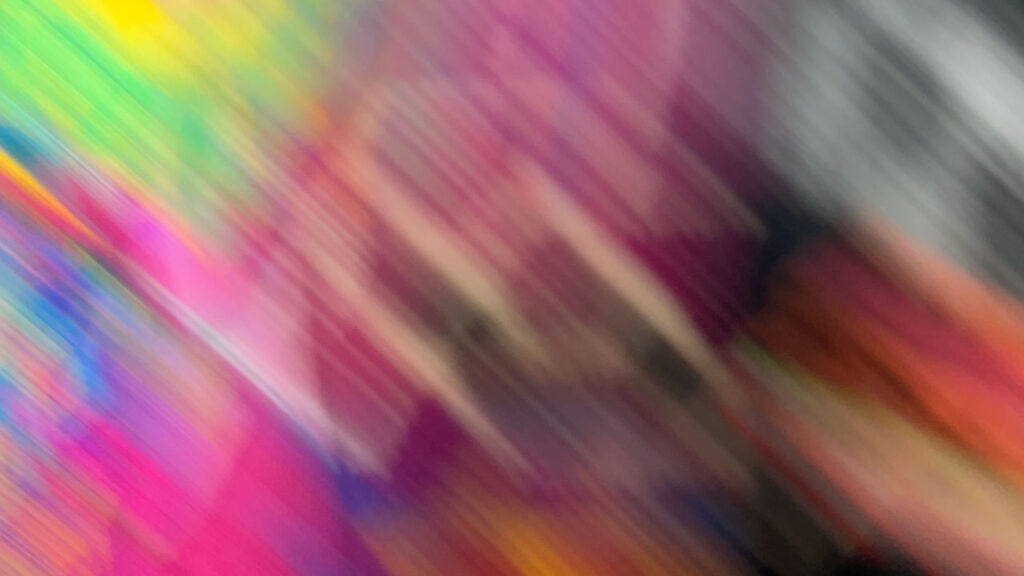
人の心を動かすこと、驚かせることが原動力になる
人の心を動かすこと、
驚かせることが原動力になる
バッグ作りにハマっていった詠子さんだが、オリジナリティを出すなら洋服などは作りたくならなかったのだろうか。疑問に思って尋ねると「直線しか縫えなかったから」と笑った。
「洋服は曲線を縫う部分が多いんですよね。直線でできるものだとランチョンマットも作ったけれど、やっぱり実用的なバッグが作ってて楽しかったんですよね」
なかでも、極めていったのは「布づくり」だ。いわゆる「パッチワーク」と言われる、数種類の生地をつなぎ合わせて一枚の布にする手法に、詠子さんはオリジナリティを感じた。色や柄、質感の違う生地を組み合わせながら、自分の感性を表現していく。詠子さんにとってバッグは、自分のアート作品を実用的に昇華させた姿だった。
その頃、世の中はハンドメイドブーム。ちょうど友人がハンドメイド作品を販売するというので行ってみたら、なんと家の玄関先でお店を広げていたという。
「私は『自分のバッグは売るレベルに達していないんじゃないか』とか『売るなら販売会はちゃんと企画しないと』とか、いろいろ考えてたんです。完璧主義でしょ。でも、玄関に座布団をおいて手作り品を販売している友人を見て拍子抜けしたというか、それでいいんだ!と思って。しかも、近所の人たちがすごく喜んで『かわいい、かわいい』って買っていくんですよ。売ってる側も買ってる側も楽しそうで、そのときに『やってみたい!』って強く思った。それがバッグを売り始めたきっかけですね」
早速、知り合いに空き店舗のガレージを借りて、販売会を企画した詠子さん。ポスターを作り、近所の人に声をかけて、いざ当日を迎えてみると、詠子さんのなかでまた新しい灯火が見つかった。
「お金になることよりも、“人が来ること”がすごく楽しかったんです。私の声がけや作ったポスターを見て、心を動かしてくれる人がいることにモチベーションが上がるんだと気づいたんですね。そういえば、雑誌を作っていたときも、自分が掲載した散策コースに『行ってきました』ってハガキをもらうと、本当にテンションが上がってたなあって」

当時、古着のアップサイクルに力を入れていた詠子さんは、知人の古着屋から洋服を仕入れてバッグに再生させる活動を行なっていた。バッグになった古着を見て、お客様が放った言葉がいまだに忘れられない、と振り返る。
「古着屋で働いていた方が私のバッグを気に入ってくれて、『古着好きってうんちくを語る人が多いんだけど、言葉ではない表現で古着を魅せる人は初めて』と言ってくれたんですね。もう、天にも舞い上がる気分でした。不要になったものをデザイン性のあるものにアップサイクルして驚かせたい!!』という気持ちがあったことに気付きました」
今でも、「kibi-ru ACTION」のイベントに人が来てくれたり、バッグを手にとってもらえたりするたびに心が震える、と詠子さんは言う。お客様から「このバッグのおかげで通勤が楽しくなりました」とか「このバッグを持つと、いろんな人に声をかけられます」と報告をもらうと、ものづくりへのエネルギーが湧いてくる。
人を喜ばせ、驚かせ、変化を起こす。詠子さんはバッグや販売会を通して、ひとつのエンターテイメントを作り上げているのかもしれない。こうして走り始めた「kibi-ru ACTION」は、この後さらに人々を驚かせていくことになる。

「この布は、本だ」民族布を愛する理由
「この布は、本だ」
民族布を愛する理由
古着のアップサイクルに邁進していた詠子さんが、現在の「kibi-ru ACTION」の顔となる「民族布」に出会ったのは、あるハンドメイドマルシェだった。ある男性が持っていた、グリーンのショルダーバッグに釘付けになってしまったのだ。それは、フィリピンの布で作られたものだった。
「フィリピンの布を管理している事務所を訪れ、布の背景を丁寧に説明してもらいました。布が作られた村、文様の意味、日本へ運んできた理由、その想いなどを聞くうちに、『これ、布じゃなくて、本じゃん!』と。それくらい、いろんなストーリーが詰まっていて、知るほどに布の奥深さにのめり込んでいきました」
その布は、元新聞記者で、翻訳家・児童文学研究家の山本まつよさんのコレクションだった。行き場を探しているという大量の布を眺めながら、詠子さんは提案していた。
「私、この大切な布をバッグにして、みなさんにご紹介したいです」
そうして2016年6月、フィリピンの布で作り上げたバッグ70点が、阿佐ヶ谷のギャラリーに並んだ。「halo-halo CRAFT展」と名付けられた展示会では、山本さんを慕う人や布好きな人々が集まって、バッグを見ながらたくさんの会話が生まれたと詠子さんは振り返る。
「すごくあったかい雰囲気で展示会ができて、『あの布がこんなふうになるんだ!』と喜んでもらえました。こんなに人を喜ばせられるんだったら、なんぼでも作ります!って思いましたよ」
その展示会から、詠子さんの周りには世界各国の民族布が集まるようになった。アジア、中南米、アフリカ……それぞれの国で生まれた布が、その国を愛する人々によって、詠子さんのもとへ運ばれてくる。また、「kibi-ru ACTION」では、山本さんのようなコレクターだけでなく、グアテマラ、タイの国際ボランティア団体からも布や民族衣装を仕入れている。刺繍やカードなどの手作り品の発注は、団体の活動費となる。
「布を扱っている国のなかには、まだまだ女性や子どもたちが生きづらい環境も多くあります。私から見たら過酷とも思える環境のなかで、鮮やかな色使いや華やかな柄を作り出せる彼女たちの前向きさ・生きる力に、とっても心を打たれる。布を通して伝えたいことがたくさんあるんですよね」
それぞれの国の文化、習慣、歴史、暮らす人々、辿ってきた道のり。一枚の布の向こう側には、途方もなく広い世界が広がっている。詠子さんはバッグを作りながら、その布に込められた多くの人たちの影を想う。
「たくさんの人影が見えると、、彼らのストーリーをどうにか形にして届けたくなるんです」
最近では、「布を“生き物扱い”してしまう」と詠子さんは笑った。フォトグラファーにも「布の息遣いを撮影してください」と頼むらしい。そういう伝え方は、一枚の布のなかに物語を見る詠子さんにしかできないことだ。

多様なチームで手を取り合う、ものづくり
多様なチームで手を取り合う、
ものづくり
民族布と合わせて「kibi-ru ACTION」のもうひとつの大切なアイデンティティが、「福祉施設と一緒におこなわれるものづくり」だ。バッグづくりの工程の一部を、東京と埼玉の2ヶ所の障がい福祉施設に委託している。
具体的には、バッグづくりで出た端材の加工作業。パッチワークのような布の切り貼りや、細長く裂いた布を混ぜた「さをり織り」を依頼している。貴重な布を「1センチも無駄にしない」という強い気持ちで、小さな小さな端材までを材料にして、一枚の布に生まれ変わらせていく。
そして出来上がるのが、アップサイクルをテーマにしたサスティナブルシリーズ『CUT』だ。「kibi-ru ACTION」のバッグを作るたびに出る端材が、障がいのある人々の手によって新たな布になり、また新たな商品となる仕組みだ。
幼い頃の詠子さんが、父の切り出した書体をスクラップブックにひとつずつ丁寧に貼り付けていたように、福祉施設で丁寧に糊付けされていく布。それを縫い子さんがミシンにかけ、「kibi-ru ACTION」オリジナルのパッチワーク布が完成する。さまざまな人の手を通って出来上がった布を、詠子さんが商品としてお客様に届けていく。
福祉施設と一緒にものづくりを始めたのは、2019年。詠子さんのある思いから、地元の施設に掛け合ったのが始まりだった。
「彼らが販売している商品を見て、なんというか、悔しさのようなものを感じました。私自身もずっと手作りでバッグを作ってきて、常に『もっといいものを作りたい』と思ってきた。その追求が、彼らにもできるんじゃないかって可能性を感じたとも言えます。デザインやストーリーを込めることができたら、もっと違うものができるんじゃないか、と」
アポなしで飛び込んだのは、福祉施設「バオバブの木 そらのいろ」という重度身体障がいのある方々を対象とした生活介護施設だ。突然、「一緒にものづくりしませんか」と飛び込んできたデザイナーとのやりとりは、もちろんすぐに前向きに進んだわけではない。一ヶ月以上も悩んだ上での「やってみよう」という返事だった。
「そらのいろ」では、もともと織物の作業があったり、染色の経験があるスタッフがいたりと、ものづくりの経験があったため、素材を民族布に置き換えるところからスタート。自分たちが織り上げた布がバッグになるのを目の当たりにして、驚きの声が上がったことを詠子さんは嬉しそうに話す。
一方、知人がつないでくれた、もうひとつの障がい福祉施設「一般社団法人ION(あいオン)」では、はさみを持つ練習から。ハギレを、さらに細かくカットして、台紙となる布に糊付けしていく。
「『適当に』とか『バランス良く』みたいな曖昧な指示は通じにくいし、糊の量の調節が難しくて。バターナイフを使ってみたり筆に変えてみたり、スタッフの方々がいろいろ試行錯誤してくれたんです。おかげで、2ヶ月後にはバッグの素材として使える布ができるようになっていました」

詠子さんとやりとりをしながら、利用者さんたちの作業をサポートしていくのは、施設で働く支援員の方々だ。福祉のプロと、ものづくりのプロ。それぞれの得意分野を持ち寄って、できあがるのが『CUT』シリーズなのだと、詠子さんは語る。
「どうして福祉施設と一緒にやるのかとよく聞かれますが、それは彼らが私にはない感性をもっているから。ものづくりには、常に新しいインスピレーションが必要です。彼らと一緒だからこそ出来上がるものがあるんですね。支援員の方からは『期待に応えられるか心配』と言われますが、どんなものでも私が必ずカタチにするので、安心してやってみてくださいと伝えています」
2019年の夏、彼らが作った布を素材としたバッグが並んだ「CUT展」には、6日間で200人が来場する反響があった。また、アパレルと革職人とのコラボレーション作品が、香港のファッションショーに起用されるなど、そのオリジナリティが注目されるようにもなっていく。
『CUT』シリーズが大手百貨店やギャラリーに並び、自分たちが関わった商品がお客様の手に渡っていく様子は、福祉施設の人々や利用者のみならず、彼らの家族にとっても嬉しいもの。ものづくりが驚きや喜びにつながる姿は、まさしく詠子さんが見たかった光景だった。

みんなで一緒に、手を結んで新しい扉を開く
みんなで一緒に、
手を結んで新しい扉を開く
詠子さんはインタビューのなかで、「kibi-ru ACTION」のことを何度か「みんなで作っている」と表現した。私が布を選んでいます、私がデザインしています、と、いくらでも「自分の作品」として押し出せるはずなのに、常に「みんな」の顔が浮かんでいるようだった。
「ひとり勝ちじゃなくてね、みんなで一緒じゃないと意味がない。『kibi-ru ACTION』に関わってくれている人みんなと一緒にゴールテープを切りに行きたいんです。その先に、それぞれが“自由に表現できる世界”を作りたい。得意なものや苦手なものは人それぞれ違うから、チームになって動くことで不得意が補える。”自由に表現する”って、みんなと一緒に動くことで可能になるのだと思います」」
あの布が、あの古着が、あのハギレが、こんな商品になるなんて!と、多くの人を驚かせてきたエンターテイナーな詠子さんだからこそ、人々は彼女から目が離せない。どんな夢を見せてくれるのだろうかと、自分の夢まで彼女に託してみたくなる。
「次は海外進出!たくさんの人たちと一緒に作ったバッグをどこか異国のショーウィンドウに飾ってみたい」
ニューヨークなのかパリなのか、おしゃれな街頭のガラス越しに、パッチワークされたカラフルなバッグが見えたような気がした。
色も素材も年代も違う、多種多彩な布を組み合わせるkibi-ru ACTION独特のパッチワークは、まるで個性あふれる人同士をつなぐ詠子さんの活動そのもの。これからも多くの人とつながりながら、どんな未来を見せてくれるのか。誰もが自由に表現できる世界——自分の好きな色を出しながら、希望を持って挑戦できる世界への道のりが、楽しみでならない。

special thanks
Mana Wilson
「物の向こうにいる人」を伝えるライター。
物の生まれた背景を伝えることが、
使う人も作る人も幸せにすると信じて、
作り手を中心に取材・執筆をおこなっています。
取材帰りにお土産を買って帰るのが大好き。
special thanks
Mana Wilson
「物の向こうにいる人」を伝えるライター。
物の生まれた背景を伝えることが、
使う人も作る人も幸せにすると信じて、
作り手を中心に取材・執筆をおこなっています。
取材帰りにお土産を買って帰るのが大好き。
Photo : EIKO SHIMANO
